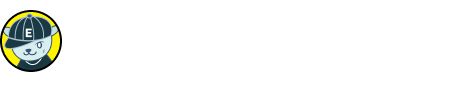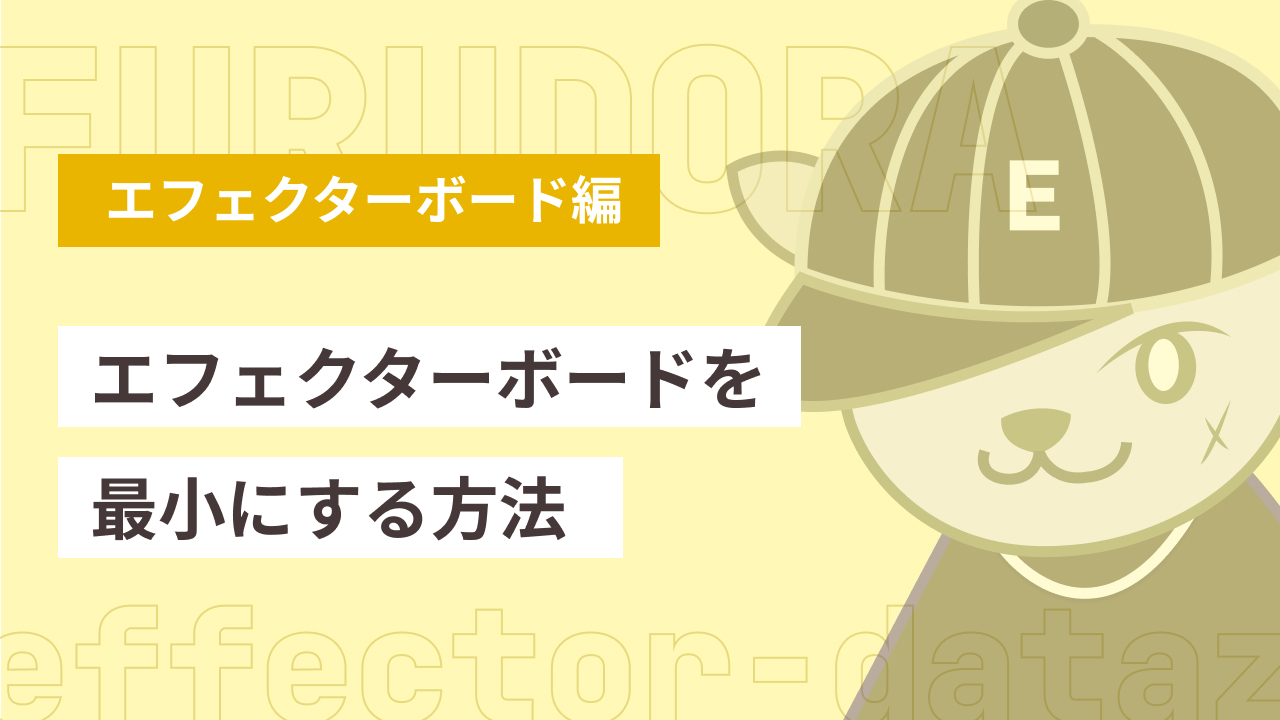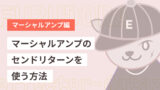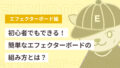こんにちは!
フルドラくん(@fulldora_kun)です。
今回は、
「エフェクターボードを最小にしたい」
「重いエフェクターボードを持って行きたくない」
「でも、マルチエフェクターは使いたくない」
といった悩みについてお答えしていきます。
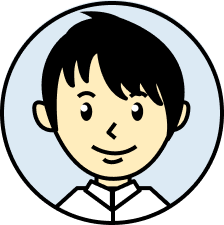
もう重いエフェクターボードは持って行きたくない。。

歪ませたアンプを有効に使おう!
エフェクターボードを最小にする方法
エフェクターをたくさん組み込んだエフェクターボードは、かっこよくて憧れますよね。
でも、いざリハーサルスタジオに持って行こうとすると、「重すぎて運べない…」なんてこともあったりします。
ミニエフェクターにするなどの軽量化することで、多少は軽くなるかもしれませんが、エフェクターボードの大きさは小さくすることは難しいでしょう。
極端ですが、マルチエフェクターを使ってしまえば、解決することかもしれません。
しかし、人によっては、コンパクトエフェクターでなんとかしたいと思う人も少なからずいるとは思います。
そこで、ぼくが実際にマルチエフェクターを使わずにエフェクターボードを最小にした方法をご紹介いたします!
歪ませるアンプを使おう
まず、オーバードライブやディストーションなどの歪み系エフェクターは、歪ませることができるアンプで代用します。
リハーサルスタジオで使う前提で言えば、マーシャルアンプを使うことが必須ですね。

アンプで歪ませることができれば、歪み系エフェクターは必要なくなるので、その分、エフェクターが減ります。
マーシャルアンプでは、JCM900やJCM2000といったモデルが多いと思います。
そのモデルであれば、必ずリードチャンネルがついてるので、そのチャンネルで使えば、アンプで歪ませることができます。
アンプの仕様や使い方をある程度、覚える必要がありますが、慣れてしまえば、「マーシャルアンプがあるなら、歪みはいらないな」と判断することができます。
ブースターは必須
歪みは、アンプで代用できると言えども、エフェクターのブースターは必須です。
ここは、エフェクターとしては削れない部分だと思います。
ブースターには、大きく分けて、「GAIN(歪み)を足すブースター」と「LEVEL(音量)足すブースター」に分けられます。
もちろん、2つの用途のブースターをあったほうが便利でありますが、最優先にしたいのは、「GAIN(歪み)を足すブースター」のほうです。
理由としては、マーシャルなどの歪ませることができるアンプだけでは、サウンドを仕上げるのに不十分なことがあるためです。
例えば、マーシャルアンプで歪ませても、高域と低域たっぷりのドンシャリサウンドしか出せません。
なので、マーシャルアンプ+αとして、ブースターは必要なのです。
チューブスクリーマーを使おう
マーシャルアンプには、中域(ミドル)が強いチューブスクリーマーを持っていくといいです。

チューブスクリーマーを使うことで、サウンドにサスティーン(音の伸び)を足すことができるので、弾きやすくなります。
また、チューブスクリーマーに似た、TS系オーバードライブでも問題ありません。
あとはディレイを持っていくだけ
あとは、空間系エフェクターのディレイを持っていくだけで、エフェクターボードを最小にすることができます。

ディレイは、極端ですが、どんなモデルでもいいと思います。
デジタルディレイやアナログディレイ、ハイエンドなど様々なモデルがありますが、使いたいモデルを選びましょう。
軽量化したい場合は、ミニエフェクターのディレイモデルを選ぶといいです。
また、マーシャルアンプでは、ディレイのつなぎ方に注意する必要があります。
歪ませたチャンネルのINPUTにディレイをつなぐと、ディレイが歪みサウンドにミックスしてしまい、かなりクドいサウンドになってしまいます。
そのため、センドリターンを使って、ディレイをつなぐことをおすすめします。
センドリターンの方法については、下記の記事にまとめてありますので、ご参考にしてください。
クリーンと歪みの使い分けはどうするの?
ここまで、エフェクターはブースターとディレイの2個で完結できます。
しかし、サウンドとしては、クリーン(もしくはクランチ)とディストーションと2種類使いたい場合もでできますよね。
そんなときは、アンプで使えるフットスイッチを使うと便利です。
例えば、マーシャルアンプ専用のフットスイッチがあります。

このフットスイッチは、マーシャルのヘッドアンプの裏に端子を挿すことができます。

マーシャルJCM2000の場合は、センドリターンの左にあります。
フットスイッチとアンプをつなげることで、チャンネルを切り替えることができるようになります。
予め、クリーンチャンネルのほうは、セッティングしておく必要がありますが、フットスイッチを使うことでエフェクターを持っていくことがなくなります。
このフットスイッチは、リハーサルスタジオで貸してもらえる場合がありますので、相談してみるといいでしょう。
エフェクターボードを最小にした事例
実際に、ぼくがエフェクターボードを最小にした事例をいくつかご紹介いたします。
メインのアンプは、マーシャルJCM2000でリードチャンネルを仕様。
使うエフェクターは、チューブスクリーマーとディレイだけです。

曲中に、クリーンサウンドとディストーションを切り替える必要はなかったので、曲の合間に、手でチャンネル切り替えボタンを押して、サウンドを切り替えていました。
リードソロがある場合は、チューブスクリーマーの後ろにクリーンブースターを入れることもありますが、必要ない場合は、この2つだけで十分演奏できました。
ミニエフェクターで、軽量化するとこんな感じです。

上のように、最小かつ軽量化すると、リハーサルスタジオに行くときの身軽さに感動しました。
さらに、電池を使えるミニエフェクターモデルにすると、ACアダプターやパワーサプライを持っていくことがなくなりますね。
また、一点補足すると、シールドはL字プラグのものが扱いやすいと思います。
リハーサルスタジオで借りれる場合は、借りたほうが楽なこともあります。
ハイエンドモデルにすると、最小でかつ多機能になるので、少しできることの幅が広くなりますね。
まとめ
今回は、エフェクターボードを最小にする方法について、解説いたしました!
エフェクターを少なくするためは、いかにスタジオのアンプを使いこなすかがポイントになってきます。
これが、JC-120などのアンプで歪ませることができない場合は、ディストーションが一個必要になってきますが、そこは、ミニエフェクターで最小にとどめたいところですね。
アンプ1台で完結することは、なかなか難しいと思いますが、あとは、エレキギターの技術を磨いていくしかないと思います。
以上、ご参考になれば嬉しいです。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!